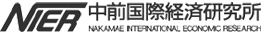新着情報
2020 / 03 / 10 16:29
News Summary
2020年3月10日
本日のラインナップ
<米国>
今回のクラッシュ、2008年と同じ点と違う点
銀行株が急落
100円ショップとClorox、数少ない上昇株に
株価とともにトランプ氏の支持率もぐらつく
<日本>
円高騰で「ステルス介入」の憶測
![]() News Summary March 10, 2020.pdf (0.93MB)
News Summary March 10, 2020.pdf (0.93MB)
詳細は添付ファイルをご覧ください
2020 / 03 / 09 16:49
News Summary
2020年3月9日
本日のラインナップ
<世界>
ウイルス感染、今後も増加へ
<米国>
米経済、ウォール街に危険過ぎるほど依存
原油の価格戦争、米国のジャンク債を危険にさらす
<中国>
ディベロッパー、デフォルトの懸念
![]() News Summary March 9, 2020.pdf (0.97MB)
News Summary March 9, 2020.pdf (0.97MB)
詳細は添付ファイルをご覧ください
2020 / 03 / 06 16:31
News Summary
2020年3月6日
本日のラインナップ
<世界>
米中、次世代スパコン開発で火花
航空業界、未曽有の損害被るか
海運業界、麻痺寸前に
<米国>
米国債イールド、ゼロに低下するか
![]() News Summary March 6, 2020.pdf (0.99MB)
News Summary March 6, 2020.pdf (0.99MB)
詳細は添付ファイルをご覧ください
2020 / 03 / 05 16:36
News Summary
2020年3月5日
本日のラインナップ
<世界>
債務危機のタネ
社債発行、1週間ぶりに再開
![]() News Summary March 5, 2020.pdf (0.92MB)
News Summary March 5, 2020.pdf (0.92MB)
詳細は添付ファイルをご覧ください
2020 / 03 / 03 16:49
News Summary
2020年3月3日
本日のラインナップ
<米国>
コロナウイルス、企業利益を圧迫
大統領選、格差のとらえ方で結果が左右されるか
米国債のイールド、1%へ接近
<中国>
経済の低迷、交通量と映画館収入で明らかに
![]() News Summary March 3, 2020.pdf (0.98MB)
News Summary March 3, 2020.pdf (0.98MB)
詳細は添付ファイルをご覧ください