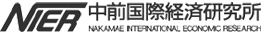新着情報
新聞掲載情報
2016年12月7日 日本経済新聞『十字路』
『「保護貿易」の論理』
グローバリゼーションの受益者は新興国と多国籍企業である。多国籍企業が賃金の安い新興国に投資をし、先進国の消費市場に輸出するビジネスモデルである。この結果、新興国は雇用を増やし、成長率を高めることができた。
こういった中国を先頭とする新興国の急速な工業化のなかで、先進国は新興国に資本財を、資源国は素原材料を輸出し、新興国は先進国に消費材を輸出する形で世界貿易は急拡大していった。
しかし、中国にみられる極端な過剰供給力の積み上げで、工業化は停滞し、世界貿易は収縮過程に入ってきている。中国の貿易依存度(輸出入額の国内総生産比)でみると、2006年の72%から直近では37%と半分近くにまで落ちてきている。
世界経済や貿易の拡大が見込めなくなったなかでは、多国籍企業の経営資源と新興国の低賃金の組み合わせによる低価格工業品を受け入れることは、先進国にとって負担である。トランプ次期米大統領の介入で問題となったキャリア社の場合、移転先のメキシコの時給3ドルに対して、インディアナ工場では上位の時給は27ドルだという。企業としては当然だが、米国経済からすると、雇用が失われ、メキシコ産エアコンが輸入され、貿易赤字が拡大していくのを見過ごすわけにはいかない。
ここで見られる「保護貿易」的傾向の特徴は、自国企業の対外直接投資を抑制しようとするところにある。中国の鉄鋼輸出のような反ダンピング課税は別に新しいものではない。多国籍企業の成長モデルが変革を求められているのだ。米国企業の本国投資への回帰を目指す法人税率の大幅引き下げなどの税制改革や規制緩和が、そのインセンティブとなる。環太平洋経済連携協定(TTP)や北米自由貿易協定(NAFTA)を新政権が望まないのは、当然の論理的帰結なのである。